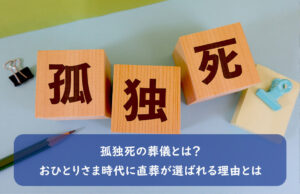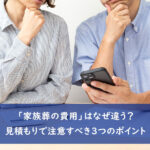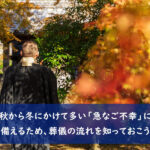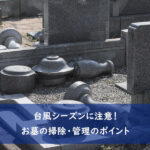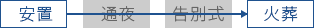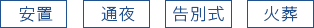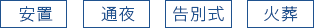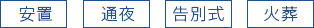お葬式のマナー
2025.07.26
直葬の香典は必要?香典辞退の理由や失礼のない伝え方
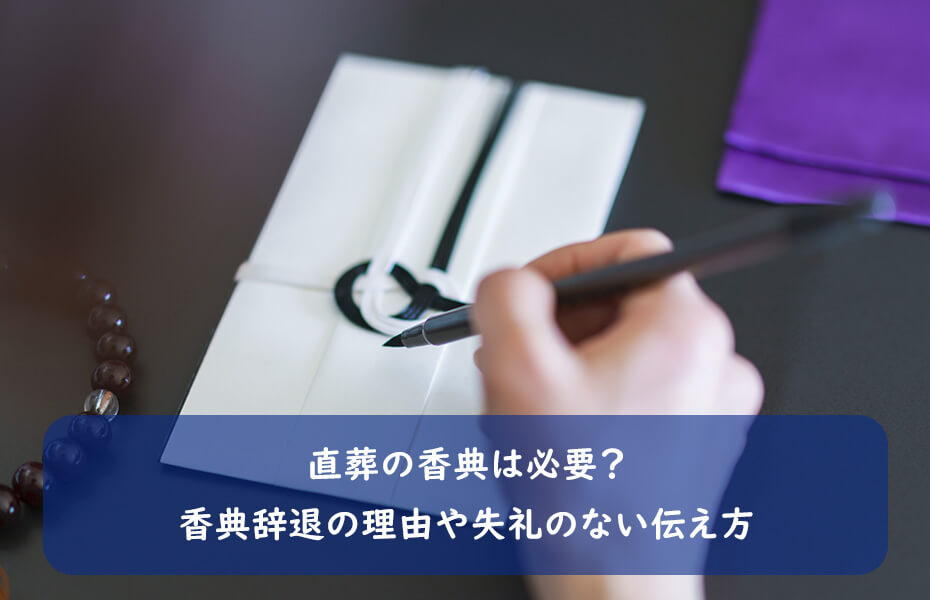
火葬場で火葬のみを行ってお別れをする「直葬」では、香典を辞退するご遺族も少なくありません。しかしその場合、事前に参列者に香典辞退の意向をお伝えしておく必要があります。
そこで今回は、相手に失礼にならない香典辞退の伝え方をご紹介します。会社への忌引き休暇申請時や訃報連絡時など、シーンにあわせた例文もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
直葬(火葬式)とは
お通夜や葬儀・告別式といった儀式を省略し、火葬場で火葬のみを行う葬儀を「直葬」または「火葬式」といいます。
火葬場でのお別れとなる直葬では、あまり多くの人をお呼びすることができないため、友人や会社の同僚などはお呼びせず、家族や親戚といった身内のみの少人数で行われることが一般的です。また、通常のお葬式で行われるような僧侶による読経や参列者による焼香といった宗教儀式も、基本的には行いません。
そのため、故人が高齢で葬儀にお呼びする人がもともと少ないという方や、宗教儀式にとらわれず、葬儀費用をできるだけ抑えたいという方などに、特に選ばれている葬儀形式です。
さがみ典礼の直葬(火葬式)には、2つのプランがあります。
※葬儀社による「役所手続きの代行」と「安置所での面会」の有無が2つのプランの違いです。
直葬に香典は必要?
身内中心で行われる直葬では、香典を辞退するご遺族も多いです。
基本的に香典は、世帯単位でお渡しするものなので、同居のご家族のみで行う直葬の場合は、原則香典は不要となります。しかし、喪主と同居していないご家族やご親族が参列する場合は、喪主やご遺族の意向で香典を辞退するかを決めることになります。
香典を辞退する際に押さえておきたいマナーとは
香典辞退とは、「香典を受け取らないこと」を意味します。家族葬や直葬のように、身内中心の葬儀が増えたことから、最近は、葬儀で香典を辞退するケースも増えてきました。
そんな中、注意したいのが香典辞退のマナーです。香典を辞退する際には、「事前に辞退の意向を伝える」こと、そして相手に「失礼にならないような伝え方を心がける」ことが大切です。
また、香典以外に、供物や供花、弔電を辞退する場合はあわせてその旨をお伝えしましょう。ちなみに直葬は火葬のみを行う葬儀なので、供花や供物を飾る祭壇や、弔電を読み上げる時間などは用意されていないません。そのため、基本的にはこれらも辞退することが一般的です。
香典を辞退する理由とは
直葬で、ご遺族が香典を辞退する主な理由は3つあります。
香典返しの負担を軽減するため
一般的なお葬式では、香典をいただいた方へのお礼として、後日、香典返しをお送りします。
香典で受け取った金額の半額〜3分の1程度のお品物をお返しすることになるため、ご遺族は、葬儀後香典額を整理し、それに見合ったお品物を用意し、発送するという作業が必要になります。
これらにかかる負担を軽減し、故人とのお別れに集中したいという想いから、香典を辞退するご遺族が多くなっています。
参列者の経済的な負担を軽減するため
故人との関係性にもよりますが、特に身内のような近い関係性の方は、数万円単位で香典をお包みすることになるため、経済的な負担は大きいです。
このような参列者の負担を軽減する目的から、香典を辞退するご遺族も少なくありません。
故人の遺志
故人が生前に、香典を辞退するよう希望しているケースもあります。その場合、故人の遺志を尊重し、ご遺族としてそれに従うのがマナーです。
香典辞退を伝えるタイミング
香典辞退を伝えるタイミングは、葬儀に参列いただく方には、葬儀案内に記載するか、訃報の連絡をする際に口頭で伝えるなど、事前にお伝えすることが望ましいです。ただし、万が一事前のご案内が間に合わなかった場合には、葬儀当日に受付などで直接お伝えするという方法もあります。
また、直葬のように身内中心で執り行う葬儀の場合、葬儀に参列いただかない方には、葬儀後に挨拶状を送ることが一般的です。挨拶状には、死亡の事実と無事葬儀を近親者のみで取り行ったご報告等を記載しますが、あわせて香典等を辞退する場合はその意向も明記しましょう。
辞退したのに香典を渡された場合の対処法
葬儀といえば「香典を持参するもの」と思っている人も少なくないため、事前に香典を辞退していても、葬儀当日に香典を持参する方もいらっしゃいます。
その場合、まずは、辞退の意向があって受け取ることができない旨を丁寧にご説明し、その上で「どうしても受け取って欲しい」ということであれば、ありがたく受け取るのがマナーです。その際、辞退の意向を伝えている手前、他の参列者の目の届かない場所で受け取るなどの配慮が必要になります。
また、葬儀当日に限らず、葬儀後に関係者から香典が送られてくる場合や、直接香典をいただく場合も、相手のお気持ちを尊重して、頑なに断ることは避けたほうがよいでしょう。
また、香典が郵送で送られてきた場合は、郵便が届いた時点で相手にお礼の一報をいれることも忘れないようにしましょう。
辞退したのに香典を受け取った場合の香典返しの考え方
事前に辞退していたのにも関わらず、香典をいただいてしまった場合、香典返しをどうするかで迷われる方は多いと思います。
基本的には、香典をいただく際に、相手から「香典返しは不要です」というひとことがなければ、身内であっても香典返しをお送りした方が無難でしょう。
香典返しをお送りする場合は、いただいた香典額の半額〜3分の1の金額を目安にお品物を選び、四十九日法要後1ヶ月以内にお送りするのがマナーです。
ちなみに、故人や家族の会社から福利厚生の一環として香典をいただいた場合は、基本的にお返しは不要です。香典の名義が会社名か個人名かを確認し、個人名の場合のみ、香典返しをお送りするようにしましょう。
(例文あり)シーン別 香典辞退の伝え方
次に、直葬で香典を辞退する際の、相手に失礼のない伝え方をご紹介します。
訃報連絡で伝える場合(口頭)
直葬では、火葬に立ち会っていただく近親者のみに、葬儀前に訃報連絡を行い、それ以外の方には事後報告とすることが一般的です。葬儀前の訃報連絡では、葬儀の内容が決まっていればその旨も合わせてお伝えしましょう。
親しい間柄の方への連絡なので、かしこまった表現ではなく、以下のようにざっくばらんにお伝えしても差し支えないでしょう。
「昨夜父〇〇が亡くなりました。葬儀は◯月◯日◯時から◯◯火葬場にて、火葬のみを行います。大変勝手ではありますが、今は何も手につかず、香典返しの用意も難しいので、香典や供物・供花等はお断りすることにしました。よろしくお願いします。」
職場に忌引き休暇の連絡と合わせて訃報を伝える場合(メール)
会社に忌引き休暇の連絡をする際は、まず直属の上司に電話で忌引き休暇の期間や葬儀の詳細について連絡を入れた後、同じ内容をメールでお送りする方法が丁寧です。
件名:忌引き休暇の取得について
本文
〇〇様(上司の名前)
いつもお世話になっております
〇〇部(部署名)の〇〇〇〇(名前)です
昨夜 私の父が逝去いたしました
◯月◯日◯時〜 ◯◯◯◯(場所)に家族のみで火葬のみを執り行います
つきましては 下記日程で忌引き休暇を申請させていただきます
◯月◯日〜◯月◯日 合計◯日間
なお 休暇中の私への連絡は
090- ◯◯◯◯- ◯◯◯◯までお願いします
ご迷惑をおかけしますが 何卒よろしくお願い申し上げます
なお 家族のみの葬儀となりますため
ご参列・御香典・供花・供物・弔電等のご厚意はご遠慮いただきたく存じます
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます
葬儀後の事後報告としての挨拶状
直葬にご参列いただかなかった関係者には、葬儀後に挨拶状をお送りして、死亡の事実と無事葬儀を執り行った旨をご報告します。その際に、香典等の辞退の意向も明記するようにしましょう。
かねてより療養中だった父〇〇が 去る〇月〇日 ◯歳にて永眠いたしました
生前は ひとかたならぬご厚誼を賜り 誠にありがとうございました
誠に勝手ながら 葬儀は近親者にて滞りなく相済ませました
お知らせが遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます
なお 故人の遺志により 御香典や供物・供花につきましては
固く辞退させていただきます
生前に賜りましたご厚情に深謝し謹んでご通知申し上げます
当日香典を持参された方へ伝える場合(口頭)
香典を辞退していたにも関わらず、香典を渡された場合は、まず以下のようにお断りをしましょう。
「故人の遺志により、御香典は辞退させていただいております。
お気持ちだけありがたくお受けいたします。」
それでも受け取って欲しいという強いお気持ちがある場合は、その想いを尊重し、ありがたく受け取りましょう。その際には、以下のようなひとことを添えると丁寧です。
「辞退のご案内を差し上げていたにも関わらず お心遣いを賜り誠にありがとうございます。」
直葬の香典辞退は、簡潔かつ丁寧に意思を伝えよう
直葬では、香典や供物を辞退するご遺族も少なくありません。その際は、「故人の遺志で」など明確な理由を添えた上で、辞退の意向を、簡潔かつ丁寧にお伝えすることが大切です。
相手との関係性によっても伝え方はさまざまですが、葬儀に参列される方には、なるべく事前にお伝えしておくことがマナーです。
さがみ典礼の直葬・火葬式
さがみ典礼は、2つの直葬・火葬式プランをご用意しています。
お通夜・告別式といった儀式を省略し、火葬のみでお見送りをする最もシンプルで最も低価格なプランです。搬送用の霊柩車・寝台車、骨壷や棺といった葬具一式、安置に必要なドライアイス(10kg)といった必要最低限のサービスがセットに含まれています。
お通夜・告別式といった儀式を省略し、火葬のみでお見送りをするプランです。お別れ直葬プランと同様のサービスに「役所手続きの代行」と「安置室での面会」が加わったプランなので、手続きの手間を省きたい方や、少しでもお別れの時間を大切にしたい方におすすめです。
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで様々な葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。また、無料の事前相談も承っておりますので、直葬に関するご不安や疑問などありましたら、お気軽にご相談ください。24時間365日いつでもご連絡をお待ちしています。
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
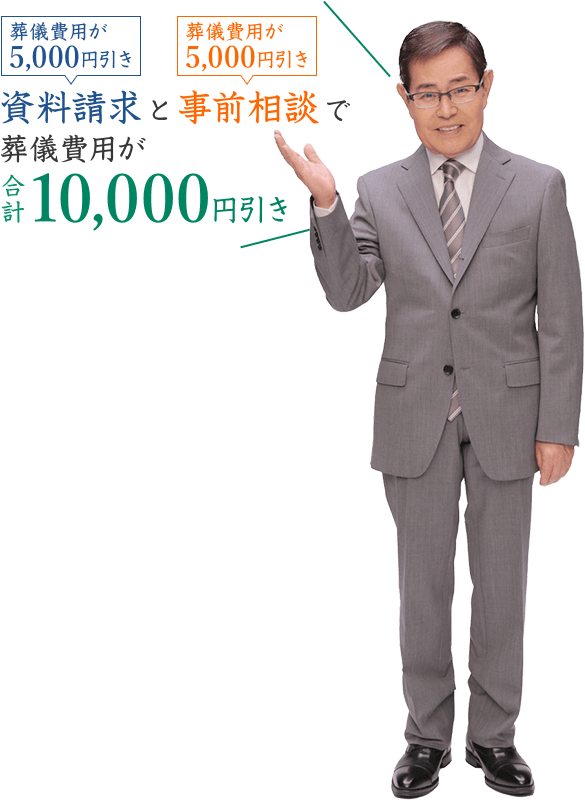
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん