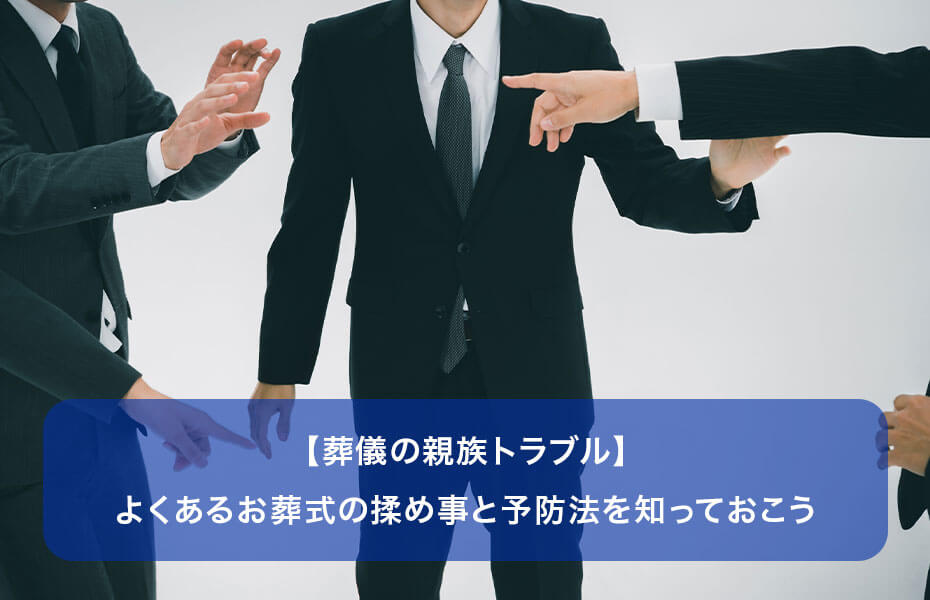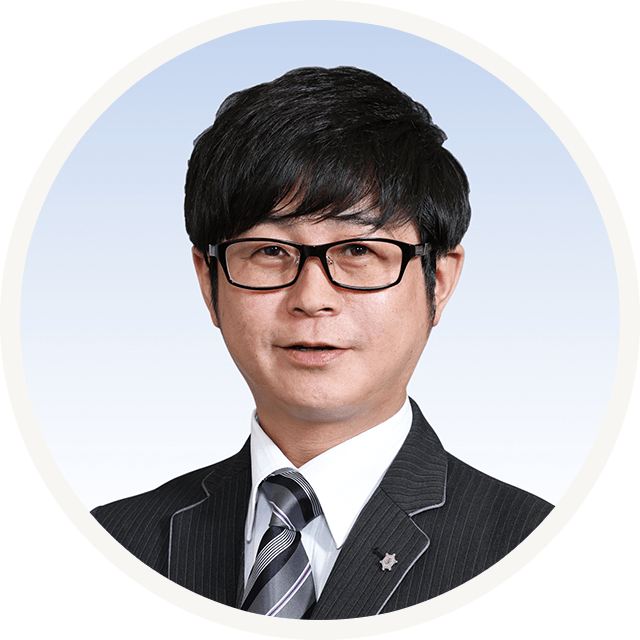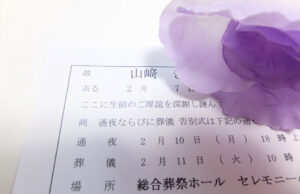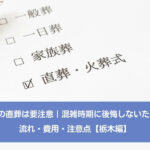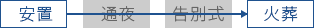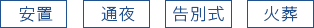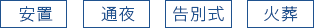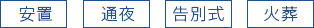家族葬
2025.04.23
家族葬はどこまで呼ぶ?参列者の範囲と家族葬でよくあるトラブル事例
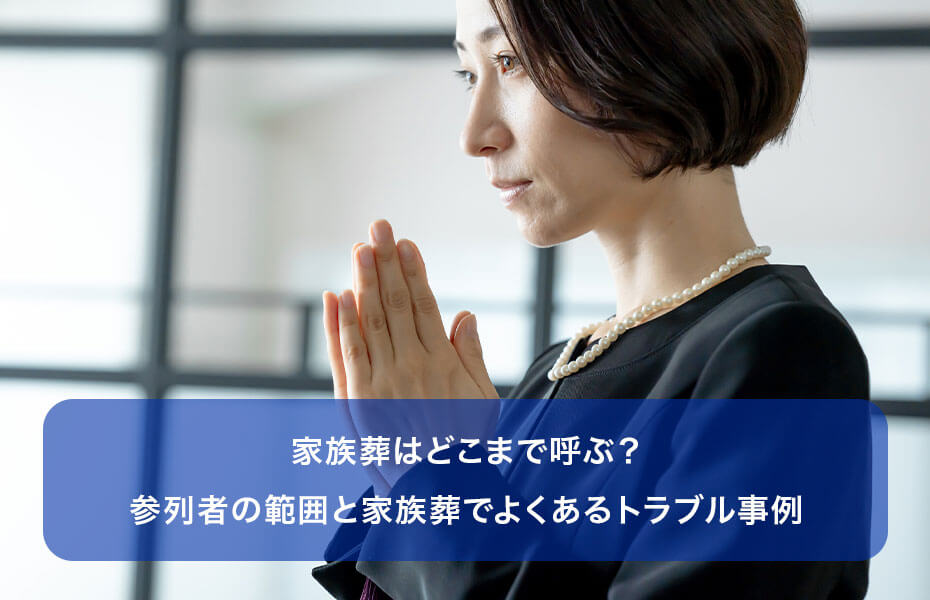
家族葬を行う場合、どこまでの人をお呼びするかで迷われる方は多いと思います。
家族葬の参列者の範囲に明確な決まりはありませんが、お呼びするべきか迷った場合は、できるだけお声がけをしておくことをおすすめします。
今回は、家族葬の参列者の範囲や家族葬の人数について詳しく解説します。これから家族葬を行うご遺族が知っておくべき家族葬でよくあるトラブル事例とその対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
家族葬の参列者の範囲
家族葬の参列者の範囲に明確な決まりはありませんが、「二親等以内の血族」が一応の目安とされています。二親等とは、故人の両親や子どもとその家族、祖父母や孫、兄弟姉妹のことをいいます。故人の配偶者の両親や兄弟姉妹も二親等にあたります。
ただし、そもそも家族葬は喪主や遺族の判断で呼ぶ人の範囲を自由に決めることができる葬儀のため、二親等でも故人との関係性が薄かった方はお呼びしない、あるいは血のつながりはないけれど親しい関係だった方はお呼びする、といったように、血縁関係に関わらず故人との関係性を考慮してお声がけをすることが大切です。
親族以外も家族葬に呼べるの?
親族以外の方を家族葬にお呼びすることは可能です。故人の親しいご友人などで葬儀に参列してほしい方がいる場合は、迷わずお声がけしましょう。
また、場合によっては、生前故人から「あの人は葬儀に呼んでほしい」などと意思表示があったり、エンディングノートに葬儀に呼んでほしい人リストが書かれていたりすることもあるかもしれません。その場合は、故人の遺志を尊重してお呼びするようにしましょう。
家族葬の人数は10〜30名程度が目安
家族葬にお呼びする人数はさまざまですが、一般的には10名〜30名程度の家族葬が多くなっています。しかし、なかには、同居のご家族のみが参列する5名程度の家族葬もあれば、親しいご友人などもお呼びした40名を超える家族葬もあります。家族葬は人数を制限する葬儀ではなく、お呼びする人を限定し、参列者の人数を決めておくことができる葬儀であることを念頭に置いておきましょう。
ただし、葬儀社のプランによっては30名以内など人数を制限していたり、追加料金がかかったりすることがあるため、大人数になる場合は、葬儀社に確認してから進めるようにしましょう。
連絡するか迷ったらお呼びしよう
参列者の範囲を決めるとき、「この人はお呼びした方がいいだろうか」と迷われる方が出てくるかもしれませんが、その場合は、迷わずお呼びすることをおすすめしています。家族葬の対人トラブルの章でも後述しますが、呼ばれなかった方からのクレームがくるなど、後々のトラブルに発展してしまう可能性があるためです。
家族葬でよくある対人トラブル
次に、家族葬でよくある親族や菩提寺、友人や近所の人など関係者との対人トラブルについて事例と対応策をお伝えします。
親族から葬儀形式に対する不満を言われる
家族葬は近年世の中に急速に浸透し、今や一般葬よりも多くの割合を占めるようになりましたが、まだまだ抵抗のある方もいるでしょう。家族葬は親しい方だけでアットホームなお見送りができることがメリットですが、「最期は多くの人に見守られながら送ってあげたい」と考える人もいると思います。葬儀や供養に対する考え方は人それぞれなので、そのような価値観の違いから、葬儀当日に親族から不満をいわれてしまうというケースも少なくありません。
トラブルを防ぐための対応策
葬儀形式や葬儀の内容については、事前に、選んだ理由や意図を明確かつ丁寧に伝えておくことが大切です。もし、故人が家族葬を希望していたのであれば、「故人の意向で」と事前に伝えておくだけでも、このような不平不満を減らすことができます。また、余裕があれば、葬儀形式や内容を決める際に親族とも話し合って決めることで、トラブルを予防することができます。
家族葬に呼ばれていない人から、後日不満をいわれる
お呼びする人の範囲を、喪主やご遺族が自由に決めることができるのは家族葬のメリットの一つですが、その分、後々呼ばれなかった人から「なぜ、呼んでくれなかったんだ」と不平・不満を受けやすくなるというリスクも含んでいます。
トラブルを防ぐための対応策
お呼びするか迷った方には、なるべくお声がけするようにすることで、このようなトラブルを最小限に抑えることができます。
お呼びしていない人が会場に現れる
家族葬が浸透してきたとはいえ、「葬儀といえば駆けつけるもの」と思っている人はまだまだいらっしゃいます。家族葬では、何らかの方法で訃報を耳にした関係者が直接会場に来てしまい、ご遺族が困惑してしまうということもよくあるトラブルの一つです。
トラブルを防ぐための対応策
このようなトラブルを防ぐため、家族葬の訃報は、葬儀後の事後報告にするということが基本となっています。忌引き休暇の関係でお伝えしなければならない会社の方などには、訃報のみを伝えて、葬儀の詳細は伏せておくようにしましょう。
葬儀後、自宅に弔問客が頻繁に訪れる
家族葬の場合、葬儀当日に参列できなかった関係者が、後日ご自宅に弔問に訪れることが、一般葬に比べて多くなる傾向にあります。ご遺族は葬儀後も四十九日法要や納骨の準備、相続等の手続きでお忙しいということもあり、弔問客対応が負担になってしまうことも考えられます。
トラブルを防ぐための対応策
訃報連絡の際に、弔問辞退の意向を伝えておくか、葬儀後しばらくは弔問を控えて欲しい旨を伝えておくとよいでしょう。もし訃報で伝えられなかった場合は、弔問に伺ってもよいかという問い合わせを受けた際に、直接お伝えしてもよいでしょう。
弔問をすべてお断りするのは申し訳ないという場合には、少しでも負担を減らすために、あらかじめ弔問に来ていただいても大丈夫な日時を指定しておいて、その時間内に来ていただくという方法も効果的です。
菩提寺に納骨できないといわれる
先祖代々お付き合いしている菩提寺がある場合は、菩提寺との関係にも注意が必要です。葬儀では、宗教儀式として故人に戒名を授け、読経を行いますが、それらの儀式を省略した場合、先祖代々のお墓に納骨できなくなってしまう可能性があることを覚えておきましょう。
特に家族葬の中でも、お通夜を省略する一日葬や、家族葬ではありませんがお通夜・葬儀・告別式を省略する火葬式・直葬は、事前に確認せずに行なってしまうと、菩提寺に納骨を拒否されてしまうということがあります。
トラブルを防ぐための対応策
菩提寺がある場合は、葬儀形式について菩提寺にも事前に了承を得ておきましょう。
万一了承を得られない場合は、葬儀形式を変えるか納骨方法を変えるかの2択になります。
香典を辞退しているのに渡される
家族葬では、香典を辞退するケースも少なくありません。しかし、香典は慣例となっているため誤って持参する参列者が出てきてしまうことがあります。また、辞退の意向があっても、どうしてもお渡ししたいというお気持ちから持参する方が出てくる可能性もあります。
トラブルを防ぐための対応策
香典辞退の意向があるにも関わらず、香典を渡されてしまった場合は、まずは「お心遣いありがとうございます。香典は辞退させていただいております」などと、感謝の気持ちをお伝えした上で、丁寧にお断りしましょう。それでも、相手がどうしても渡したいという場合は、相手の気持ちを尊重して受け取るということも選択肢の一つです。ただし、他の参列者の手前一度はお断りすることがマナーです。
また、事前に香典を辞退している場合の香典返しは不要とされていますが、相手によっては香典返しやお礼状をお送りしても失礼にはあたりません。
家族葬ならではのトラブルにご注意を
家族葬は、参列者の範囲を限定しているため、親しい方々でアットホームなお見送りができるというメリットがある反面で、参列したくてもできない方が出てきてしまうというデメリットもあります。そのため、一般葬では起こることのなかった思わぬトラブルが潜んでいる場合があるので注意が必要です。
それらのトラブルは事前に把握しておくことで問題を最小限に抑えることができます。そのためにも、このコラムを参考にしていただけたらうれしいです。
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。
また家族葬では、24万円・36万円・48万円・60万円・72万円と、必要な内容に応じて複数のセットプランを設けていますので、まずはお見積もりからでも、お気軽にご相談ください。
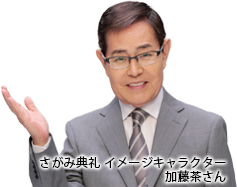
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
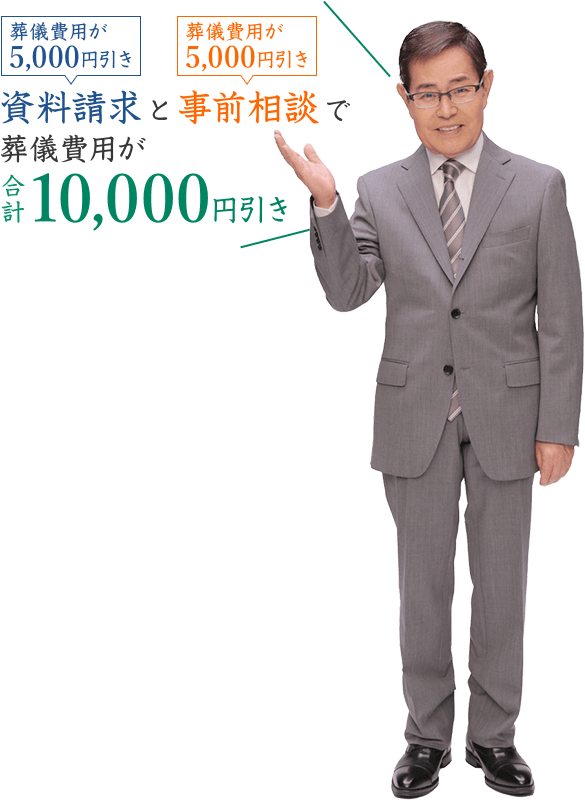
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん