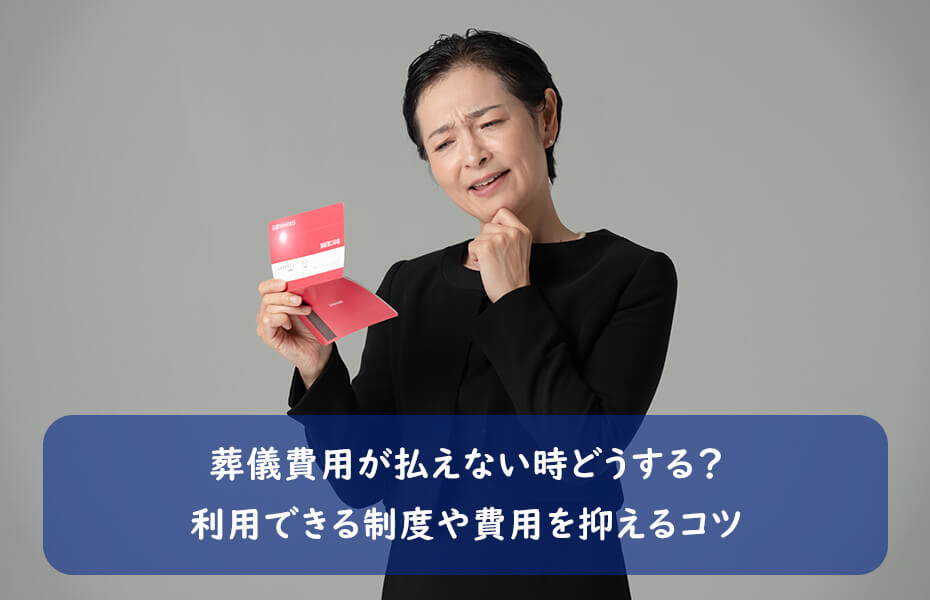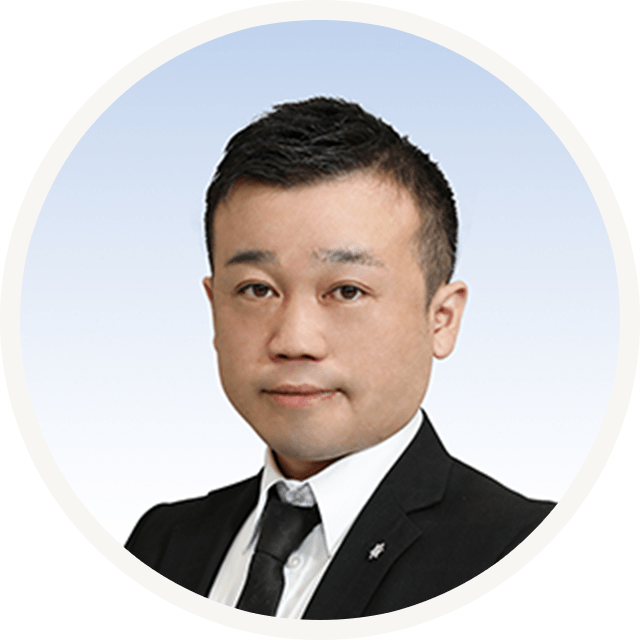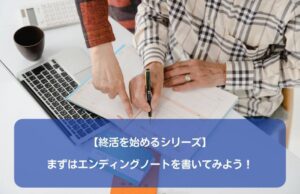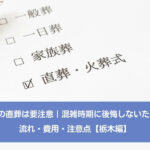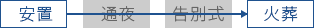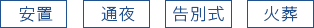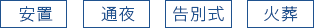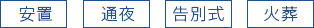家族葬
2025.08.21
葬儀保険は家族のためにできる生前準備。メリット・デメリットを知ろう
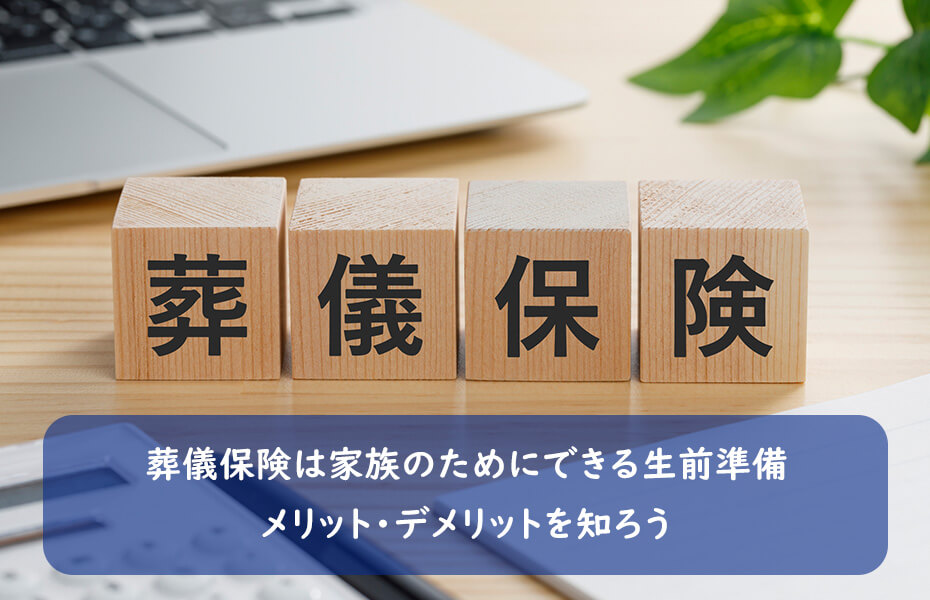
自分が亡くなった後、葬儀費用はご家族が負担することになります。
葬儀となるとまとまった金額が必要になるため、最近は、「なるべく子どもに迷惑をかけたくない…」などの理由から、葬儀保険を検討する人も増えています。
そこで今回は、終活の一環として「自分で葬儀費用の準備をしておきたい」という方のために、葬儀保険のメリットや注意点を解説します。終身保険や互助会との違いにも触れていますので、生前に葬儀費用を準備しておきたいという方は、ぜひ参考にしてください。
自分の死後、家族が負担する葬儀費用はどのくらい?
葬儀費用の相場は、葬儀の規模によっても変わりますが、平均で118.5万円という集計結果が出ています。※1
また、葬儀形態別の葬儀費用の平均額と最も多い価格帯については、以下のような集計結果があります。
【葬儀形態別 葬儀費用比較】※2
| 葬儀形態 | 葬儀費用の総額 | 最も多い価格帯 |
|---|---|---|
| 一般葬 | 161.3万円 | 120万〜140万 |
| 家族葬 | 105.7万円 | 60万〜80万 |
| 一日葬 | 87.5万円 | 20万〜40万 |
| 直葬(火葬式) | 42.8万円 | 20万〜40万 |
この金額は、宗教者にお渡しするお布施を含まない金額です。
ちなみに、葬儀におけるお布施の相場は、宗旨宗派などによっても異なりますが、10万〜50万円程度といわれています。
葬儀費用は誰が支払う?
葬儀費用は、喪主が支払うことが一般的です。
喪主は、配偶者や子どもが務めることが多くなっています。配偶者がいない場合は子どもが喪主となりますが、子どもが複数いる場合は、長男または長女が務める可能性が高くなります。
また相続財産がある場合、それを葬儀費用に充てれば問題ないと考えるかもしれませんが、相続はスムーズに進んで3~4ヶ月、遺産分割協議に時間がかかった場合は1年以上かかることもあります。そのため、相続財産を葬儀費用に直接充てることは、あまり現実的ではありません。
葬儀費用のよくあるトラブルの一つに、「誰が支払うか」で相続人同士の意見が食い違うことが挙げられます。子どもたちが、お金を出し合って葬儀費用を負担することもできますが、誰がいくら払うかの割合で揉めてしまうケースもよくあるトラブルの一つです。
最近は、このようなトラブルを避けるために「自分で葬儀費用を準備する」という方が増えています。
自分で葬儀費用を準備したい人のための「葬儀保険」とは
自分で葬儀費用を準備する選択肢の一つに葬儀保険があります。葬儀保険とは、葬儀を行う際に必要な費用をまかなうための保険のことで、少額の保険料で50万円〜300万円程度の葬儀費用を準備できるというものです。
葬儀保険のメリット
葬儀保険のメリットは、以下の通りです。
月々500円以下の少額で葬儀に備えられる
加入時の年齢や、加入する葬儀保険によっても月々の保険料は異なりますが、葬儀保険は、掛け捨てであることに加え、死亡保証に特化しているため、一般的な生命保険に比べ賭け金を割安に抑えることができます。
そのため、月々の負担を抑え、無理なく葬儀に供えることができます。
高齢でも加入しやすい
葬儀保険は80歳を超えても加入でき、90歳を過ぎても補償を継続できる保険が多数あります。多くの生命保険が60代、70代を上限にしているのに比べ、高齢の方でも加入しやすいのが葬儀保険の特徴です。
健康上の不安があっても加入しやすい
葬儀保険には「告知型」と「限定告知型」の2種類があり、持病のある方でも限定告知型であれば、医師の診断なく告知のみで加入できることが多くなっています。
一般的な生命保険の場合、加入時に詳細な告知が必要になり、告知内容によっては医師の診断が必要になることもありますが、それに比べると加入ハードルが低く入りやすいというメリットがあります。ただし、持病によっては加入できないこともあるので注意しましょう。
保険金の支払いが早い
葬儀保険の中には、請求書類を出した翌営業日に保険金が支払われるものもあり、比較的支払いまでの期間が短いのが特徴です。葬儀代の支払いは葬儀後1週間〜10日以内に設定されていることが多いため、現金が早く手元に入るのも葬儀保険のメリットといえます。
保険金を葬儀会社に直接支払ってもらえる場合もある
保険会社によっては、保険金を直接葬儀社に支払ってもらえるサービスを実施している場合があります。
葬儀後は、法要の準備や相続手続きで慌ただしい時間をお過ごしになるかと思いますが、そちらを利用することで、支払いの手間を省き、やるべきことに集中することができます。
ただし保険料が葬儀代金を下回る場合は、差額分をご遺族が支払うことになるため注意が必要です。
葬儀代以外にも利用できる
葬儀保険は、葬儀社に支払う費用以外にも、宗教者へのお布施、仏壇、お墓、年忌法要の費用、入院費、遺品整理の費用などにも充てることができます。
葬儀保険のデメリット
次に、葬儀保険のデメリットをお伝えします。
掛け捨てのため貯蓄性がない
葬儀保険は、基本的に保証期間1年の掛け捨て型のため、貯蓄性はありません。その分保険料は割安になっていますが、契約途中で解約してもそれまで支払った保険料に見合った解約返戻金を受け取ることはできません。
若いうちに加入すると元本割れする可能性がある
葬儀保険は掛け捨て型のため、加入期間が長い場合は、支払った保険料の方が受け取る保険金よりも高くなってしまう「元本割れ」が起こる可能性があります。
年齢に応じて保険料やもらえる保険金が変動する
葬儀保険には、「保険金定額型」と「保険料定額型」の2種類があります。
保険金定額型は、もらえる保険金の額は一定ですが、月々の保険料が年齢に応じて上がっていくというもので、保険料定額型は、月々の保険料は一定ですが、もらえる保険金が年齢に応じて下がっていくというものです。
このように、月々の保険料が上がってしまう、もしくはもらえる保険金が下がってしまうという変動がある点は葬儀保険のデメリットといえます。
失敗のない葬儀保険の選び方
次に、葬儀保険を選ぶ際のポイントをお伝えします。
健康面が不安な方は「引受基準緩和型」「無選択型」がおすすめ
葬儀保険は、生命保険に比べて持病のある方でも入りやすい保険ではありますが、それでも健康状態によっては入れない可能性も考えられます。
もしご不安がある場合は、比較的告知項目の少ない「引受基準緩和型」か、告知不要の「無選択型」を選ぶことを検討してみましょう。
必要な葬儀費用に見合った保険料にする
もし、葬儀のイメージがある程度固まっていて、ご自身の葬儀に必要な費用の目安が見えている方は、その金額に合わせた保険金額を設定するようにしましょう。
冒頭でもお伝えした通り、葬儀費用の平均は100万円前後となることが多いため、一般的には、保険金が100万円以上の葬儀保険を選んでおくと安心です。
保険金受け取りまでの期間を確認する
葬儀保険は比較的保険金受け取りまでの期間が短く設定されていますが、検討する際にはどのくらいのスピード感で支払ってもらえるのかを確認しておきましょう。
一般的に、葬儀代は葬儀後1週間から10日以内に支払うことが多いため、期限内に支払えるよう保険料の支払いが早めのものを選ぶことをおすすめします。
責任開始期を確認する
葬儀保険には、契約日のほかに責任開始日が設定されています。責任開始日とは、契約が執行される日を意味します。
たとえば、契約日が8月1日で、責任開始日が8月25日だったとした場合、万が一8月20日に契約者がお亡くなりになったとしても保険金は支払われないため注意が必要です。
葬儀保険以外の葬儀費用の備え方
葬儀保険以外にも、終身保険や互助会に加入することで葬儀費用を賄うこともできます。
終身保険に加入する
終身保険に加入しておけば、自分の死後、受取人に死亡保険が支払われます。
終身保険の場合、保証が一生涯続くため、保険料や保険金の変動はなく、支払われた保険金は受取人個人の財産とみなされ、遺産分割協議の対象にもなりません。そのため、終身保険の保険金を葬儀費用に充てることも可能です。
ただし、月々の保険料は葬儀保険よりも割高になってしまうことや、加入できる年齢の上限が葬儀保険に比べて低く設定されていることなどがデメリットとして考えられるため、どちらがご自身に合っているかは、よく検討して決めましょう。
互助会に加入する
互助会とは、相互扶助を目的に会員が月々出し合った賭け金を積み立てるシステムのことをいいます。葬儀保険と違って積立型のため、積み立てたお金は無駄になりにくいというメリットがあります。
さらに、積立金は、葬儀に限らず、結婚式や成人式、七五三などのライフイベントに充てることも可能です。
ただし、葬儀社や葬儀プランの選択肢が限られている点や、積立金だけでは葬儀費用を賄えないことが多い点はデメリットといえます。
葬儀保険はメリット・デメリットを踏まえて検討しよう
昨今、終活意識の高まりとともに「葬儀費用で家族に迷惑をかけたくない」と考える人は増えています。葬儀保険は、万が一に備える保険の中でも、加入ハードルが低く、高齢でも加入でき、月々の負担も少ないというメリットがありますが、一方で、掛け捨てであることや、長期加入で元本割れをしてしまうリスクなどデメリットもあります。
そのため、ご自身の年齢や状況を踏まえて、よく検討して決めることをおすすめします。
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。
また、葬儀や終活に関するご不安ごとや疑問・質問などにお答えする無料の事前相談も行なっております。お電話・インターネット・メールなどから24時間365日無料で承っておりますので、ご不明点があればどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
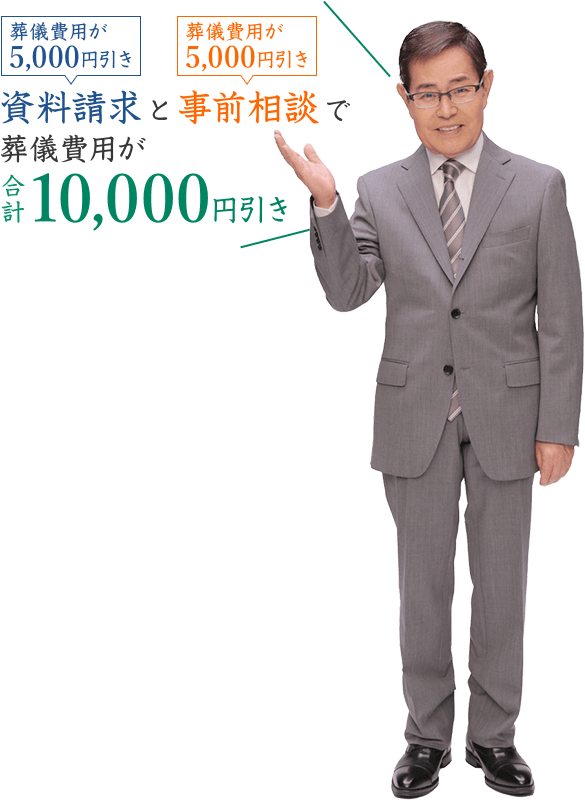
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん