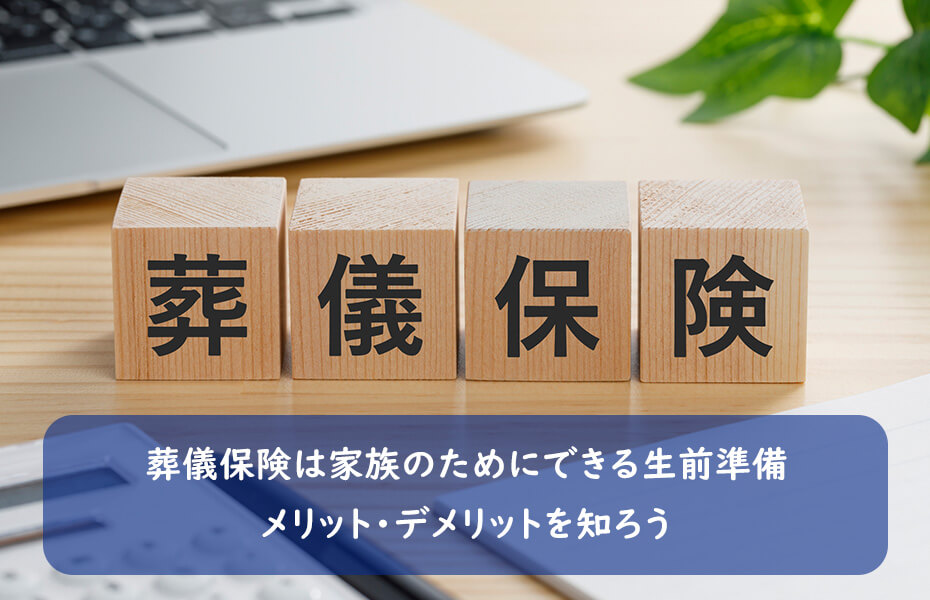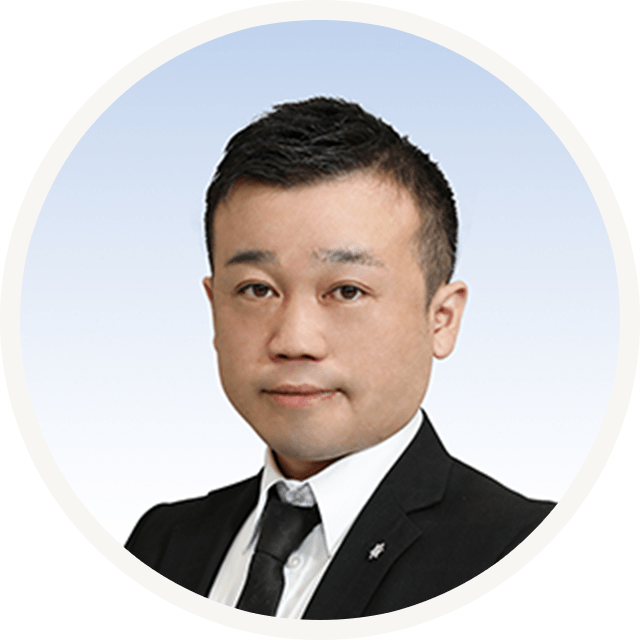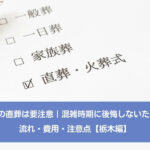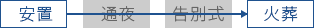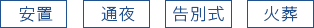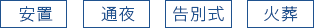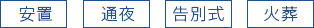家族葬
2025.08.02
葬儀費用が払えない時どうする?利用できる制度や費用を抑えるコツ
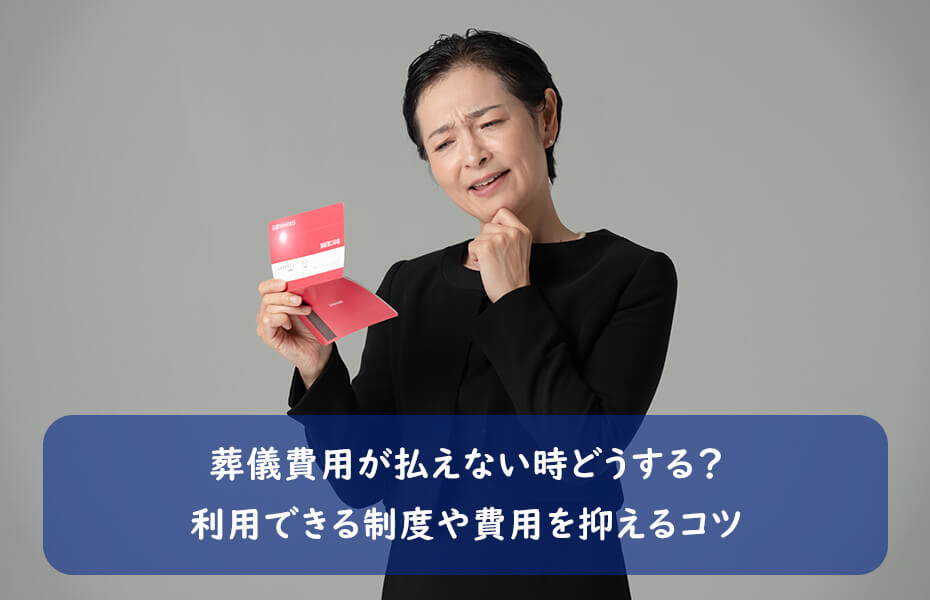
葬儀は、誰もが人生の最後に経験する重要な儀式である一方で、「突然のことで葬儀費用が支払えない」「今すぐ支払う余裕がない」という方も少なくありません。
そこで今回は、葬儀費用が払えない時の対処法をご紹介します。葬儀費用を補填するために利用できる制度や、費用を抑えるコツなどもお伝えしますので、これから葬儀を行うご予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
葬儀費用の相場
ひとことで葬儀といっても、その前後には搬送・安置・納棺・通夜・告別式・火葬・収骨など様々な儀式やプロセスがあり、必要なものも多岐にわたるため、思ったよりも費用が高くついたと感じてしまうことがあるかもしれません。
2024年に発表されたお葬式に関する調査では、葬儀にかかった平均額は118.5万円※1でした。この金額には、宗教者に支払うお布施は含まれていないため、実際には10万〜数10万円単位の費用がプラスで必要になります。(無宗教葬の場合を除く)
まずは、葬儀にどのような費用が必要なのかを把握するために、葬儀費用の内訳をみていきましょう。葬儀費用の内訳は以下のとおりです。
【葬儀費用の内訳(平均)】
- 基本料金(葬儀社・火葬場に支払う費用):75.7万円
- 飲食費:20.7万円
- 返礼品費:22万円
- +宗教者に渡す費用:宗旨宗派やお寺との関係性によって異なる
※参照元:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
基本料金には、会場のレンタル代やスタッフの人件費、棺や祭壇などの葬送用品に加え、ご遺体の安置に必要なドライアイスや、霊柩車などによるご遺体の搬送代などが含まれています。
また、飲食費は、通夜振る舞いや精進落としといった会食にかかる費用、返礼品費は、会葬御礼や香典返しにかかる費用、宗教者に渡す費用は、読経供養や戒名授与のお礼として僧侶など宗教者にお渡しするお布施やお車代などのことをいいます。
葬儀費用が払えない時の対処法
葬儀費用が高くて支払えないという場合は、以下の対処法を検討してみましょう。
故人の死亡保険で支払う
故人が生命保険に加入していれば、死亡保険を受け取ることができます。まずは、故人が加入していた生命保険がないか調べてみましょう。もし加入していれば、保険会社に連絡し、早急に手続きを進めるようにしましょう。
死亡保険は死亡保険金受取人からの請求であれば、1週間前後で保険金が入金されることが一般的です。一方、葬儀費用の支払いは、葬儀後1週間以内としている葬儀社が多いです。死亡保険を受け取るには、戸籍抄本や印鑑証明など入手に手間がかかる書類を揃える必要があるため、支払いに間に合わせるためには、早めの手続きが肝心です。
親族で分担して支払う
葬儀費用は、喪主または施主が負担することが多いですが、誰が支払わなくてはならないという決まりはありません。費用が足りない場合は、親族で分担して出し合うことをおすすめします。誰がいくら負担するかについては、親族間でよく話し合って決めるとよいでしょう。
葬儀ローンを利用する
葬儀ローンとは、葬儀社と金融機関が提携して実施しているローンのことです。葬儀社と葬儀の打ち合わせを行う際に、その場で申し込みができるため申し込みの手間は少なく、また、即日審査が可能になることも多いので、まずは、葬儀社に相談してみましょう。
葬儀ローンを使うことで、分割で支払うことができるようになり、一度に支払う金額を減らすことができます。ただし、ローンである以上は手数料がかかってしまうため、最終的な総額は高くなってしまうことは承知しておきましょう。また葬儀ローンは、宗教者へのお布施のように、当日現金で手渡しする費用には適用できないので注意しましょう。
クレジットカードの分割払いを利用する
クレジットカードでの支払いが可能な葬儀社であれば、カードの分割払いやリボ払いを利用する方法もあります。こちらも、手数料はかかってしまいますが、一回に支払う金額は安くなるため、すぐに大きなお金は支払えないが、少額ずつなら支払えるという場合におすすめです。
ただし、カードの限度額は事前に確認しておきましょう。葬儀費用は高額になることが多いので、限度額を超えてしまう場合も考えられます。限度額を超えてしまうと利用できなくなってしまうため注意が必要です。
葬儀費用を補うために使える制度
次に、葬儀費用を補うために使える制度をいくつかご紹介します。
遺産分割前の相続預金の払い戻し(仮払い制度)
基本的に、故人の預貯金は相続財産になるため、勝手に引き出したりすることはできません。しかし、この制度を利用することで、他の相続人の同意が得られていない状態でも、遺産分割前の故人の預貯金から必要な額(上限あり)を引き出すことができるようになります。
ただし、この制度を利用することで、故人にマイナスの財産があった場合でも、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。
生活保護受給者のための葬祭扶助制度
故人が生活保護受給者で一定の条件を満たしていた場合、国が葬儀費用を負担してくれる葬祭扶助制度を利用できる場合があります。
この制度を利用して行える葬儀は、お通夜や葬儀・告別式を省略した火葬のみの葬儀となりますが、実質負担0円で葬儀を行うことができるため、生活保護を受給している方は、まずは、ご自身が対象かどうかを確認してみましょう。
葬祭扶助制度について相談先は、担当のケースワーカーや市区町村の福祉課です。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費
故人が国民健康保険・後期高齢者医療保険の受給者だった場合、葬儀後に申請することで、葬祭費を受け取ることができます。申請先は故人の住民票があった市区町村役場です。金額は自治体によっても異なりますが、5〜7万円の自治体が多くなっています。
葬儀が行われた日から2年以内に申請する必要があるため、忘れずに申請しましょう。
健康保険の埋葬料
埋葬料は、故人が会社員や公務員で健康保険の被保険者だった場合、その被保険者によって生計を維持されていた遺族に対して支払われる給付金です。もし遺族がいない場合は、埋葬を行なった人に支払われます。支給額は一律5万円で、加入していた健康保険組合によってはプラスアルファの付加給付がある場合もあります。
詳しくは、故人の加入していた健康保険組合に問い合わせてみましょう。
葬儀費用を抑えるためにできること
上記以外にも、葬儀費用を抑える方法があります。
葬儀形態を見直す
下記に、葬儀形態別の平均費用を記載しました。そちらをみてもわかるとおり、葬儀形態によってかかる費用は大きく異なります。
もし、費用を抑えたい場合は、参列者の範囲を限定し少人数で行う「家族葬」や、お通夜を省略し一日で行う「一日葬」、お通夜や葬儀・告別式を省略し、直接火葬場でお見送りをする「直葬」などを検討してみてもよいでしょう。
【葬儀形態別 葬儀費用(平均)】
- 一般葬:161.3万円
- 家族葬:105.7万円
- 一日葬:87.5万円
- 直葬 :42.8万円
※宗教者へのお布施は含まれない費用です
参照元:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
参列者の数を減らす
葬儀の参列者の人数を見直してみることも費用を抑える方法の一つです。参列者の人数が少なければ少ないほど、返礼品や会食の料理にかかる費用を削減することができます。
不要なオプションをつけない
費用が高いと感じたら、不要なオプションが付いていないかも確認しましょう。葬儀社に詳細なプラン内容を説明してもらい、不要な項目があれば外してもらうようお願いするとよいでしょう。
複数の葬儀社に見積もりをとる
葬儀社を選ぶ際は、複数社に見積もりを依頼し、比較検討することも大切です。葬儀社によってプランに含まれている内容が異なるため、同じ葬儀内容でも、最終的な金額に差が出る場合があります。また、見積もりを依頼する際には、内訳まで入った詳細な金額がわかるものを依頼しましょう。
葬儀費用を生前に準備しておく
最近は終活意識の高まりとともに、生前に葬儀費用を準備してご家族の負担を減らしたいと考える人が増えています。
最後に、葬儀費用をご自身で用意する方法についても簡単に触れておきたいと思います。
葬儀保険に加入する
葬儀保険は葬儀を行う際に必要な費用をまかなうための保険です。月々500円〜の保険料で、数十万〜300万円程度の葬儀費用に備えることができます。高齢であったり持病があったりしても加入しやすいなどのメリットがありますが、掛け捨てのため貯蓄性がないなどのデメリットもあります。
終身保険に加入する
終身保険に加入していれば、死亡時に保険金が受け取れるので、それを葬儀費用にあてることができます。保証も充実しており貯蓄機能がある点などはメリットですが、加入できる年齢の上限が葬儀保険に比べて低めに設定されていたり、月々の保険料が高くついてしまったりというデメリットもあります。
互助会に加入する
互助会とは、事前にお金を積み立てることで葬儀費用に備えられるシステムのことです。保険のように現金が支給されるわけではありませんが、いざというときに葬儀に必要なサービスを受けることができます。
使える制度や支払い方法を工夫して葬儀費用を削減しよう
葬儀費用はまとまった金額が必要になるため、急な支払いに戸惑ってしまうことも多いと思います。そんな時には、国の制度や補助金を利用して、費用を抑える工夫をすることが大切です。また、プラン変更だけでも大幅に費用を抑えられることもあるので、葬儀プランや費用のことでわからないことがあれば、葬儀社に相談をしてみましょう。
さがみ典礼では、お電話・インターネット・メールなどから無料の事前相談を承っています。葬儀のことでわからないことはもちろん、ご不安ごとや懸念点などがあれば些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。お客様のニーズに合わせた幅広い料金プランをご用意していますので、まずはお見積もりだけでも、お気軽にご相談ください。
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
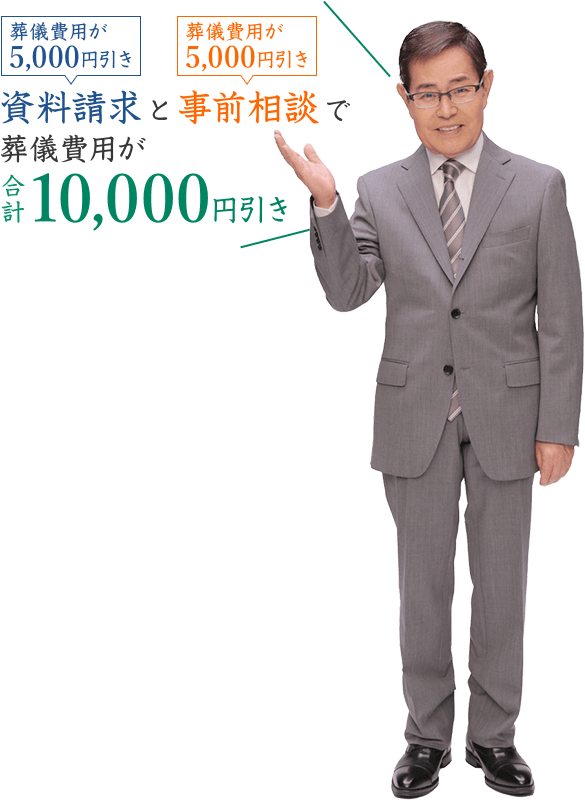
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん