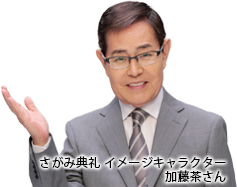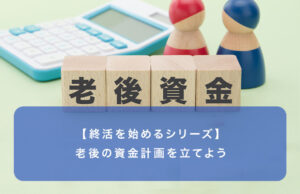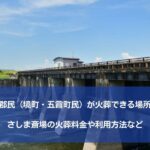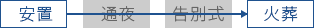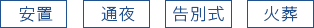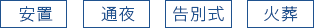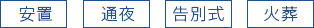法事・法要
2025.06.26
遺骨を自宅で保管するには?手元供養のメリットや注意点を解説

故人のご遺骨は、四十九日の忌明けを迎えたタイミングでお墓や納骨堂などに納骨されることが一般的ですが、なかには、そのままご自宅で保管するという方もいらっしゃると思います。
今回は、ご遺骨の自宅保管を検討されている方に向けて、保管場所や保管する際の注意点などを解説します。また、ご自宅で安置しているご遺骨も、ゆくゆくは管理されている方の健康状態やご家庭の状況などによって、自宅以外の供養先を考える必要が出てくると思います。
そのような場合に備えて、最終的な供養先の考え方もあわせてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
そもそもご遺骨は自宅で保管できる?
一般的にご遺骨は、四十九日法要後、お墓や納骨堂などに納骨され、お手元から離れていきますが、ご自宅などに保管しておくことも可能です。
墓地や埋葬等に関することが定められた法律「墓埋法」には、ご遺骨の埋葬場所について「墓地以外の場所に埋葬することを禁止する」という法律はあるものの、自宅で保管することについて特段禁止はされていません。ただし、ご遺骨を自宅の庭などに埋葬してしまった場合は、墓地以外に埋葬したとみなされ法律違反となってしまうので注意が必要です。
手元供養の方法
ご遺骨の一部、または全部をご自宅など身近な場所で保管することを手元供養といいます。手元供養には、遺骨アクセサリーやミニ骨壷等を利用してご遺骨の一部を手元に保管しておく分骨供養と、すべてのご遺骨を手元に保管しておく全骨供養の2種類があり、分骨供養の場合、手元に残さないご遺骨は、通常通り墓地等に納骨することになります。
ここでは、手元供養の方法をいくつかご紹介します。
【骨壷のまま自宅保管する】
すべてのご遺骨を骨壷のまま保管する方法です。分骨をして、一部のご遺骨をミニ骨壷に収めて保管するという方法もあります。
【アクセサリーなどにして身につける】
遺骨ペンダントや指輪、キーホルダーなどのアクセサリーに加工して、常に身につけることができる方法です。自分でアクセサリーに遺骨を入れることができるものや、業者に加工してもらうものなどがあり、場合によってはご遺骨を細かい粒子状にする粉骨が必要になることもあります。アクセサリーなどにご遺骨を収めて持ち歩くことができるため、外出先でも故人を身近に感じることができるというメリットがあります。
【遺骨プレートに加工する】
故人のご遺骨をパウダー状に粉砕し、セラミックなどの素材と混ぜて加工し、遺骨プレートにする方法です。インテリアとして飾れるため、骨壷に比べて場所を取らないというメリットがあります。
【粉骨して真空パック加工をする】
ご遺骨を粉骨し真空パックする方法です。骨壷よりもコンパクトにまとめることができ、真空パックすることでカビや湿気から守ってくれるというメリットがあります。
ご遺骨を自宅で保管するメリット・デメリット
次に、ご遺骨を自宅保管する際のメリットとデメリットをお伝えします。
自宅保管のメリット
・ずっと一緒にいられる安心感がある
自宅に保管したり、アクセサリーとして身につけたりすることで、故人が常に身近にいてくれるような安心感を得ることができます。
・いつでもお参りができる
常に身近にあるため、思い立ったらすぐにお参りをすることができます。
・お墓の購入費用がかからない
手元に保管しておく分には、お墓を購入する必要はありません。
自宅保管のデメリット
・遺骨管理の手間がかかる
カビが生えないよう気をつけたり、災害時の落下や破損に気をつけたりする必要があります。
・親族等の理解が得られない場合がある
お墓への納骨という一般的な供養方法を望む人は多いため、周囲から理解を得られない可能性も考えておく必要があります。
・家族以外のお参りが難しい
自宅保管のため、お墓参りのように家族以外が気軽にお参りをすることが難しくなってしまいます。
・将来的な供養方法を考えておく必要がある
遺骨を管理している人が亡くなった後のことも考えておく必要があります。もし、何もせずにいた場合、将来的に家族や親族に余計な手間をかけることにもつながってしまいます。
ご遺骨は自宅のどこで保管する?
火葬を終えたご遺骨は、四十九日の忌明けを迎えるまで後飾り祭壇に安置されますが、四十九日を過ぎたタイミングで後飾り祭壇は解体することが一般的です。忌明け後も、ご遺骨をご自宅に保管しておく場合、どこに安置すればよいのでしょうか。
ここではいくつかの方法をご紹介します。
仏間の一角や仏壇の近くに安置する
仏間や和室がある場合は、その一角に専用スペースを設けて安置するとよいでしょう。また、仏壇がある場合は、仏壇の近くに専用の台などをおいて安置してもよいです。ただし、本来、仏壇は、本尊を安置する場所ですので、仏壇に直接骨壷を置くことは避けるようにしましょう。
人によっては、後飾り祭壇を解体せずに、そのまま活用するという方もいらっしゃいます。
リビングなどに専用スペースを作る
仏壇や仏間がない場合、家族が集まるリビングなどに専用スペースを設けるのもよいでしょう。リビングに合うデザインの骨壷を選んだり、インテリアになじむよう遺骨プレートに加工をしてもらうなどの方法も検討してみましょう。
保管の際に注意すべきポイントは?
ご遺骨を自宅管理する際に、注意すべきポイントは、直射日光と湿気です。直射日光を避けることはもちろんですが、1日のうちに温度変化が激しい場所も、ご遺骨の結露や劣化の原因になってしまうので避けるようにしましょう。
また、ご遺骨は湿気に弱いため、お風呂場や台所など水回りに近い場所は避けましょう。湿度が高い場所を避け、なるべく風通しのよい場所に保管することをおすすめします。一度カビが生えてしまうと、再度焼くことでしか改善できないため、適切な場所で保管することが大切です。
【自宅での保管場所で注意するポイント】
- 直射日光のあたらない少し暗めの場所
- 風通しのよい場所
- 昼夜の温度差が少ない場所
最終的な供養方法について
手元供養を希望した場合でも、管理している人がお亡くなりになった後のことを考えて、最終的な供養方法を考えておく必要があります。いつまで自宅で保管するかについても、家族と相談して決めておくとよいでしょう。
その後の供養方法については、以下の方法が考えられます。
菩提寺がある場合は、菩提寺の墓地に納骨する
先祖代々お付き合いしているお寺(菩提寺)がある場合は、そのお墓に納骨することが最も自然な方法です。まずは、菩提寺に相談してみましょう。
新しくお墓を建てる
墓地を探し、新しくお墓を建てるという方法もあります。ただし、お墓を建てるには2~3ヶ月程度の期間と数十万〜数百万のまとまった費用が必要になります。墓地選びや石材店選びなど必要な手続きも多いため、期間と予算に余裕を持って望むようにしましょう。
永代供養墓に納骨する
永代供養墓とは、ご遺族に代わってお墓の管理や供養を任せることができるお墓や納骨堂のことで、「お墓の継承者がいない」「子どもに負担をかけたくない」、「費用を抑えたい」などという方に選ばれている供養方法です。具体的には、納骨堂、永代供養付きの個人墓や合祀墓、樹木葬などの選択肢があります。
散骨する
散骨とは、ご遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養方法です。散骨は、法律に触れることはありませんが、粉末状にしないで散骨してしまうと死体遺棄罪に抵触してしまう可能性があるため注意しましょう。また、散骨する場所によっては、条例に触れてしまう可能性もあるため、葬儀社など、信頼できる業者が提供している散骨サービスを利用することをおすすめします。
さがみ典礼の海洋散骨はこちら
ご遺骨の自宅保管は、カビ・結露防止のため適切な場所で管理しよう
ご遺骨を自宅で保管することは、直射日光や湿気を避け、昼夜の温度差の少ない場所に保管するなど、適切な管理が必要です。しかし一方で、常に故人を身近に感じられるという安心感も得ることができます。
故人やご家族にとって「最善の供養を」とお考えの場合、自宅保管も選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
また、葬儀や葬儀後の供養方法について迷われている場合は、葬儀社の無料相談を活用するのがおすすめです。
さがみ典礼では、お電話・インターネット・メールなどから、無料の事前相談を承っています。24時間365日いつでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼の事前相談(無料)はこちらから
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで様々な葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。また、お客様のニーズに合わせた幅広い料金設定と地域に根差したサービスで、様々な葬儀プランをご用意していますので、まずは、お見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
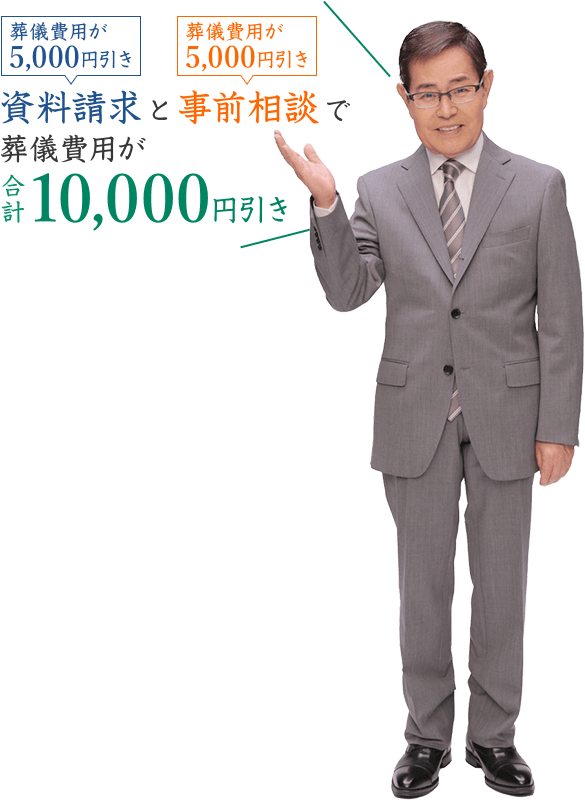
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん