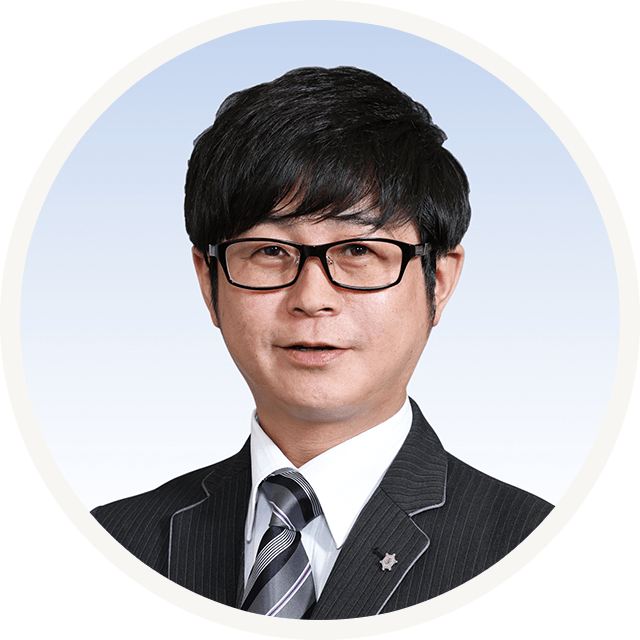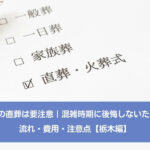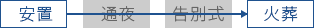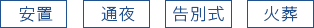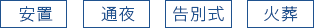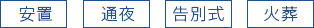家族葬
2025.04.16
葬儀費用は誰が支払う?喪主以外が払うケースやよくある親族トラブルの対処法
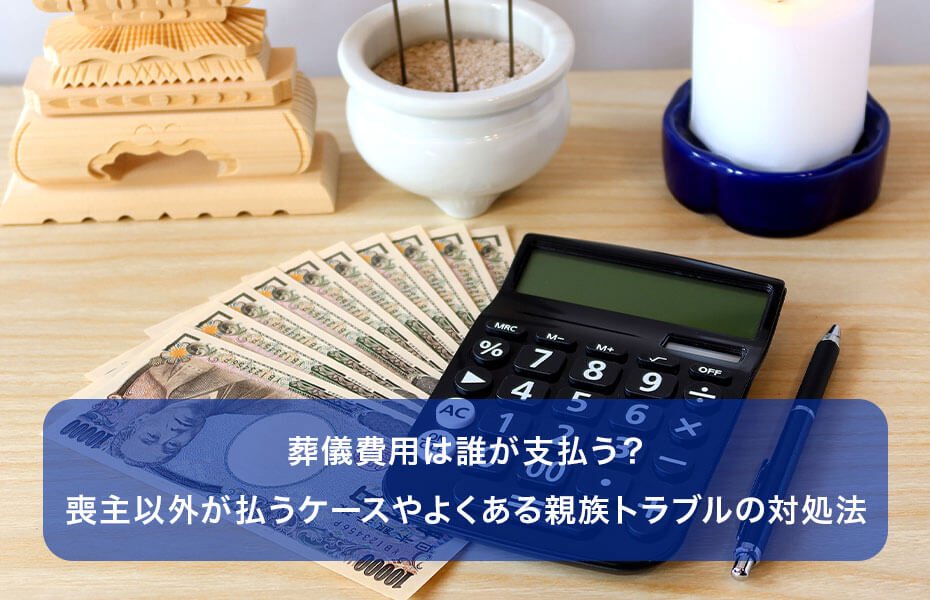
一般的に葬儀費用は、喪主が支払うことが慣例となっています。しかし、数十万、数百万単位の費用となるため、喪主だけでは負担しきれない場合もあるでしょう。
今回は、葬儀費用を喪主以外が支払うケースについて解説します。葬儀費用の支払い時に起こりやすいトラブルと対処法についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
葬儀費用は喪主が支払うのが慣例だが絶対ではない
葬儀費用は一般的には喪主が支払うことになっていますが、法律で決められているわけではないため、絶対に喪主が支払わなければならないというものではありません。喪主は、遺族の代表として葬儀の内容などを決定する立場にあるため、葬儀費用についてもすべてを把握している存在です。そのため支払いも喪主が行う方がスムーズであるという理由から、喪主が葬儀費用を支払うケースが多くなっています。
葬儀費用を喪主以外が負担するケースとは
喪主以外が支払うケースとしては、「相続人が分割して支払う」「施主が支払う」「故人の財産から支払う」の3つの方法がありますので、順番に解説していきます。
1.相続人が分割して支払う
兄弟や姉妹など相続人が複数いる場合、話し合って葬儀費用を出し合うケースがあります。たとえば3人兄弟だったとして、3人で葬儀費用を等分する場合もあれば、それぞれの事情を考慮して出せる人が多く出すというケースもあります。
基本的には葬儀費用から香典額を差し引いた金額を、各相続人同士で分けることになります。話し合いで不満なく解決できるようなら任意の額でよいですが、下記のような計算式に基づいて各人の負担額の目安を算出してもよいでしょう。
【葬儀代の相続人の負担額の目安】
葬儀代の相続人の負担額 =(葬儀代−香典)× 法定相続分※
※法定相続分とは、相続人が複数いる場合の各人の相続割合のこと
2.施主が支払う
葬儀では、場合によっては喪主のほかに「施主(せしゅ)」を立てることがあります。そうすることで、施主は葬儀費用を負担し、喪主は葬儀の運営全般の責任者となるというように役割分担をすることができます。具体的には、喪主が高齢の母親である場合に肩書きだけ母親に喪主を務めてもらい長男が施主を務めるケースや、喪主に経済的余裕がない場合や未成年の場合などに、親戚や友人が施主を務めるケースなどさまざまなケースが考えられます。
3.故人の財産から支払う
故人に財産があれば、故人の預貯金から葬儀費用を支払うことも可能です。ただし、故人の死後、故人の預貯金はすべて相続財産となるため、たとえ口座の暗証番号を知っていたとしても、勝手に引き落とすことは避けた方がよいでしょう。できれば生前に本人から了承を得て必要な費用をおろしておくことが最もスムーズな方法ですが、それができず、死後に故人の預貯金からお金をおろす場合には、仮払い制度を利用するか、遺産分割協議を先に行うかの、いずれかの方法をとることが必要になります。
・仮払い制度を利用する場合
仮払い制度とは、遺産分割協議完了前でも故人の預貯金から一定額まで引き出すことができる制度のことです。相続人一人からの請求でも引き出すことができるため、相続人同士の話し合いが難しい場合にも利用可能です。
一般的には、故人が亡くなったことを銀行に知らせると、故人の口座は凍結されてしまい遺産分割協議が完了するまで当該口座からの引き出しはできなくなってしまいますが、この仮払い制度を利用することで、凍結された状態でも故人の預貯金からお金を引き出すことができ、葬儀代や当面の生活費に充てることができるようになります。
ちなみに、仮払い制度を利用して引き出せる金額は以下の通りです。
【仮払い制度で引き出せる金額】
死亡時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1、または150万円のいずれか低い金額
※一つの金融機関につき150万円までが上限となっています。
【仮払い制度の申請方法】
直接、故人の預貯金のある銀行に申請する。
【仮払い制度の注意点】
仮払い制度を利用して、一度遺産に手をつけてしまうと、万一の時に相続放棄ができなくなってしまうことを念頭に置いておきましょう。相続放棄ができないと、故人に借金などマイナスの財産がある場合には、負の遺産を背負ってしまう可能性があります。
・遺産分割協議を先に行う
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。故人の死後に発生する葬儀費用は、原則として遺産に含まれない費用となりますが、相続人全員が認めれば、遺産分割協議書に葬儀費用の負担も記載することができるようになります。
葬儀費用を誰が払うかでよくあるトラブル
次に、葬儀費用を誰が払うかでよく起こりがちなトラブル事例と対処法を、いくつかお伝えしたいと思います。
負担割合について揉める
複数で費用負担をする場合、誰がどの程度負担をするかで揉めることがあります。「同居して故人の面倒を見てきたから、その分葬儀費用は免除してほしい」「子供が多いから経済的に余裕がない」など、それぞれに家庭の事情がある中での話し合いとなるため、落とし所を見つけるのに苦労することがあるでしょう。
そのため、葬儀費用を複数の人で支払う場合は、均等に分けるのか、年齢や所得などに応じて分けるのかなど、あらかじめ話し合ってルールを決めておくことをおすすめします。決めたルールについては書面に残しておきましょう。
香典の扱いについて不満が出る
香典を遺産に含めるのか、含めないのかで揉めることもよくあります。しかし、基本的に香典は、会葬者から喪主への贈与とみなされるため喪主の財産になります。
つまり、あまりないとは思いますが、香典を葬儀費用に充ててもまだ余るという場合、その香典は喪主のものになるということです。ただ、たとえ葬儀で余ったとしても、余った分は四十九日法要や一周忌などの法要に充てられることが多く、故人の供養のために使い果たしてしまうことがほとんどです。
先に立て替えたことによるトラブル
折半してくれると思っていた相手に後日葬儀代の半額を請求したら断られてしまったというケースもあります。暗黙の了解で折半するものだと思っていても、きちんと約束をしていないと相手にとっては寝耳に水ということもあり得ます。また、過去に「〇〇の葬儀代は折半して払おうね」という口約束をしており、その約束を一方が覚えていて、一方は忘れてしまっているというケースもあると思います。
葬儀費用を複数人で支払う場合は、事前に誰がどの程度支払うかの割合を取り決めておき、きちんと書面に残しておくことが大切です。最も確実にトラブルを回避できる方法としては、遺産分割協議で合意を得た上で、遺産分割協議書に記載をしておくことです。
葬儀費用はいつまでに支払う?
葬儀費用は、葬儀後1週間〜10日以内に支払うことが一般的です。現金または銀行振込による支払いが多いですが、葬儀社によってはクレジットカードやコンビニ払いができるところもあるので、葬儀社との事前打ち合わせの際に確認しておくとよいでしょう。葬儀後は、法要や納骨の準備、相続の手続きなどで何かと慌ただしい時期でもあるため、支払い方法についても事前に把握しておくとスムーズです。
栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。
また家族葬では、24万円・36万円・48万円・60万円・72万円と、必要な内容に応じて複数のセットプランを設けていますので、まずはお見積もりからでも、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼へのご依頼・お問い合わせはこちらから
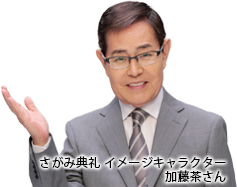
業界最安水準で最上級のおもてなし
さがみ典礼の
安心ご葬儀プラン
お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。
ご葬儀のご依頼・
ご相談はお電話で
さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん
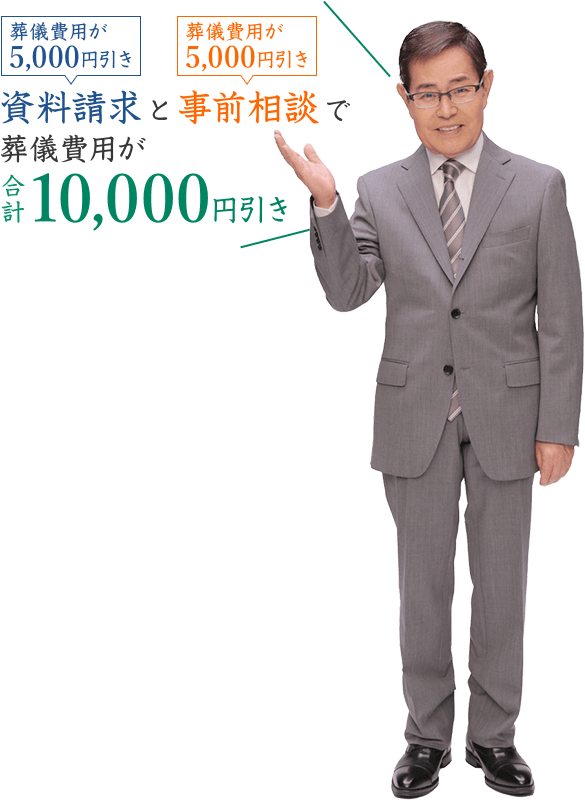
ご葬儀の準備も
さがみ典礼で
-
その日からすぐに葬儀費用が
最大20%割引になる -
いざという時慌てないために。
葬儀場見学も可能
さがみ典礼イメージキャラクター
加藤茶さん